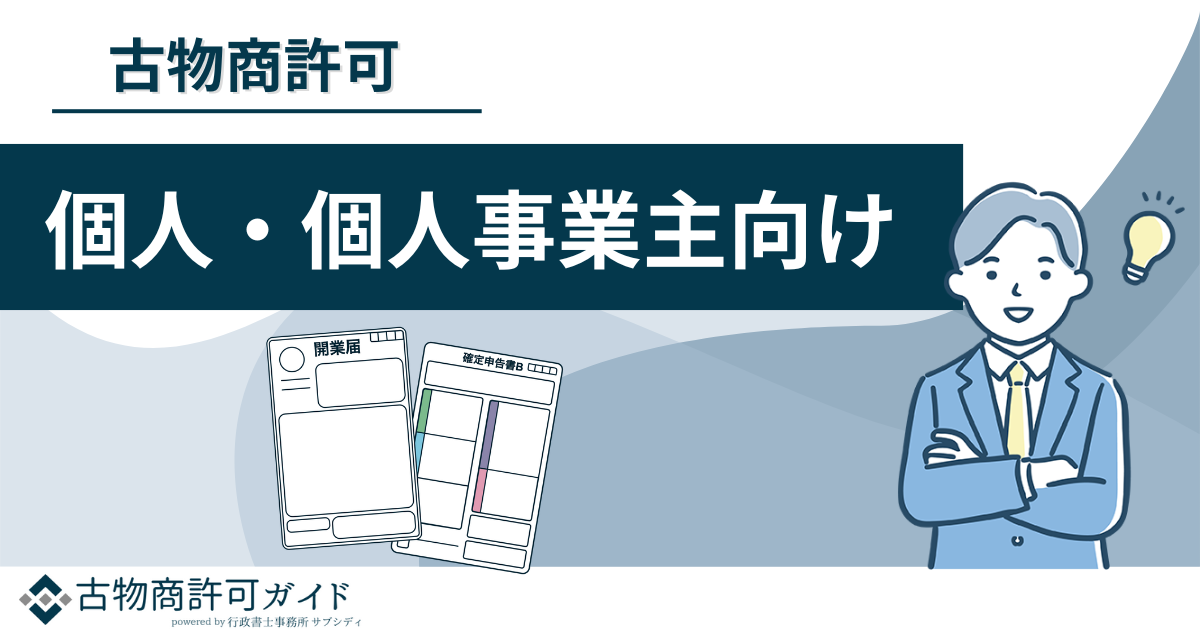古物商は、個人事業主でも始めやすいビジネスとして人気があります。
個人事業主の古物商許可は、法人と比べると必要書類も少なく行政書士報酬も安い傾向にあります。古物商許可の取得は行政書士に依頼することが一般的です。
古物商許可を取得して、新しいビジネスを始めていきましょう。
- 古物商の許可は個人名義で取得できる
- 営業を管轄する警察署へ申請書を提出する
- 自宅を営業所にするのは難しいので注意が必要
今回は、事業を始める上で必須の古物商許可について見ていきます。
個人事業主の古物商許可の取り方
古物商許可を取得するには、法定要件を確認し、警察署へ申請書を提出しなければなりません。
- 要件と取扱品目の確認
- 必要書類の収集
- 申請書類の作成
- 手数料の納付と警察署への申請
- 古物商許可証の受け取り
行政書士に取得の依頼をする際であっても、古物商許可の取得の全体の流れは把握しておきましょう。
要件と取扱品目の確認
個人事業主が古物商許可を取得するためには、いくつかの要件を満たしていなければなりません。
もし当てはまらない場合、時間をかけて要件をクリアするようにしなければならないものもあります。古物商許可の取得を考えている場合は前もって確認をしておきましょう。
欠格要件に該当しないこと
古物商営業を行う場合、次の欠格要件に該当してはいけません。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 刑罰を受けたことのある者
- 暴力団等に属する者若しくはその関係者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されそれから5年が経過していない者
- 心身の故障により業務を適正に実施できない者
- 未成年者
個人事業主がこの欠格要件に当てはまる場合は、許可を取得することはできません。
また、古物商営業を行う営業所には管理者を設置する必要があります。管理者が個人事業主と別の人物である場合、管理者もこの欠格要件に該当していてはいけません。
年齢制限
古物商許可を行う場合、特に年齢制限はありません。しかし欠格要件にあるように、原則として未成年者は古物商の営業を行うことはできません。
ただし、例外があります。個人事業主が許可を持っている場合、相続で古物商営業を引き継ぐことがあります。
相続人が未成年者であっても、その相続人の法定代理人が欠格要件に該当しなければ、古物商許可を相続し行うことができます。
また法定代理人が認めた場合も、未成年者でも古物商営業を行うことが可能です(民法第6条)。
この際、未成年者がその営業を行うときはその登記をしなければならないとされています(商法第5条)。
これは「未成年登記」とよばれます。また管理者においては、どのような場合であっても未成年者はなることができません。
取扱品目の確認
古物は全部で13種類の品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪・原付
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工事類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
自身の取り扱う古物の種類について、「主たる品目」を必ず選択し登録する必要があります。
またそのほかにも取り扱う品目があれば、それを申請書の「取り扱う品目」の欄に記載をしておかなくてはなりません。この取り扱う品目については後から追加することも可能です。
必要書類の収集
古物商許可を申請する際には、指定された書類を準備する必要があります。その主な書類は以下のものとなります。
- 許可申請書 別記様式第一号(その1~その4)
- 略歴書
- 誓約書
- 個人事業主及び管理者の住民票(本籍地記載あり・マイナンバー記載なし)
- 個人事業主及び管理者の身分証明書
- (必要な場合のみ)URLの使用権原疎明資料、営業所の使用承諾書など
申請書類は申請先の警察署によって若干異なることがあります。事前に確認をしておくとよいでしょう。
申請書類の作成
申請書の様式は、警視庁のホームページにアップされています。いろいろなパターンの書類がありますので、どの書類が必要なのかがわかりづらいこともあります。
古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する各警察署です。申請先の警察署が、それぞれ記載例や必要書類の一覧を手引きとして作成していることがありますので、参考にするとよいでしょう。
身分証明書などの個人の確認書類については、役所に行って取得をします。郵送での取得もできますが、返送までに時間がかかることがありますので前もって準備をしておくことをお勧めします。
手数料の納付と警察署への申請

申請書類がそろったら、管轄の警察署の生活安全課にて申請を行います。申請書類の内容確認には時間を要します。
その場で確認してくれることもありますが、中には一旦書類を預かり後日に受付となる場合もあります。
内容の確認ができ申請可能な状態となったら、申請手数料をおさめるように指示があります。古物商許可申請にかかる申請手数料は19,000円です。
手数料は基本的に収入印紙にて納めます。収入証紙は警察署内で販売していますので、事前に準備をしておかなくても大丈夫です。
この申請手数料は、審査に要する手数料となります。よって審査の結果、許可を取得することができなかったり、申請を取り下げしたとしても返金はされません。
古物商許可証の受け取り
警察署での標準処理期間は、通常で約40日です。
審査が完了すると連絡が来ますので、無事に許可が下りた場合は許可証を受け取りに申請先の警察署に行くこととなります。
受取人は申請者本人である必要があります。本人が行くことができない場合は、申請先の警察署に相談をしてください。委任状等で対応してくれることがあります。また、受取の際に本人確認書類が必要となりますので、持参するようにしてください。
警察署は平日の16時までしか受付をしてくれない場合が多いです。事前に連絡をして、受け取る時間を決めておいたほうが良いでしょう。
古物商許可の取得費用!個人と法人の違い
古物商許可を申請する際にかかる費用は下記のものとなります
- 申請手数料
- 個人確認書類(住民票、身分証明書)取得代
- 古物プレート 購入代
- 古物台帳 購入代
- 行政書士に依頼する場合は、報酬代
申請手数料は、全国一律で19,000円です。住民票や身分証明書は、役所にて取得することができます。一通につき300~400円です。
個人事業主と管理者の分が必要となります。個人事業主が管理者も兼ねる場合は、一通で大丈夫です。
許可を取得した後、古物プレートを営業所に掲げる必要があります。
古物プレートはネットや専門業者に依頼をして購入することができます。1,000円くらいのものから、品質にこだわると数万円のものまでたくさんの種類があります。
古物台帳の記載も義務付けられていますが、最近では電子で記録を取ることもできますのでご自身にあった方法を選択してください。
古物商許可においては、行政書士に依頼をすることで手間も時間も短縮することができます。
その際の報酬代は、平均して50,000円ほどです。個人事業主で行政書士に依頼をした場合の金額の総額は、だいたい80,000円ほどとなります。
法人と個人での費用の違い
申請手数料は、法人であっても同じ19,000円です。住民票などの確認書類は、役員および管理者全員分の書類が必要となってきます。
古物プレートや古物台帳も、営業所が複数ある場合は一つずつ必要になってきます。また、古物商許可の行政書士報酬は、法人より個人事業主であるほうが割安に設定されています。
個人事業主が古物商許可を取得する際の注意点
古物商許可を取得する前に注意すべきポイントがいくつかあります。特に、個人事業主として取得するのか先に法人化すべきかは重要なポイントです。
- 個人で取得したものを法人の活動で利用できない
- 開業届は古物商許可の取得後に提出
- 自宅を営業所にするのは難しい
- 副業でも古物商の営業ができる
- 古物商許可取得後に6か月以内に営業開始しなければならない
注意点について詳しく見ていきましょう。
個人で取得したものを法人の活動で利用できない
個人で古物商許可を有している人が、その人の所属する企業等においてその許可を利用し営業することは認められていません。
また、古物商許可を取得している個人事業主が法人化した場合、その古物商許可を継続して法人にて利用することもできません。
個人事業主と法人化した会社は、全くの別物として扱われます。法人化を検討している個人事業主が許可を持っている場合、古物商許可を改めて取得する必要があるのです。
法人化する際は新規で取得し直す
法人化を検討している個人事業主で古物商許可を取得していない場合は、法人化を先にしてから許可を取得したほうが良いでしょう。
個人事業主として許可を取得した場合は、早めに古物の営業を行うことはできます。しかし、許可申請を個人と法人とで2回行わなくてはならなくなります。
費用も労力も2倍かかってしまいます。また、法人化し新たな許可が下りるまでには時間がかかります。
個人事業主として継続した取引相手がある場合は、無許可期間が発生しその間は取引を行うことができなくなります。
許可を取得するタイミングは、ご自身の状況にあわせて検討するようにしましょう。
開業届は古物商許可の取得後に提出
開業するには、商売や事業を始める際に管轄の税務署に事業を開始すると言った旨を申告をしなければなりません。その際に提出する書類が「開業届」と言われるものです。
開業届には、主に下記の項目の記載が必要です。
- 開業者の基本情報(氏名・住所等)
- 仕事の概要
- 事業開始予定日
- 働く場所
- 収入(所得)の種類
開業してから古物商許可を取得するとなると、2か月ほど時間がかかってしまいます。
その間は古物に関する営業を行うことはできません。
また古物商の許可がなければ、事業の開始予定日を記載することができません。
働く場所についても、許可申請書に記載した営業所となります。先に古物商許可を取得しておけば、開業届の内容も正しく記載できます。
また開業したらすぐにでも事業として行うことができます。ただし、古物商の営業を開始したとしても開業自体は急いでする必要はありません。
自宅を営業所にするのは難しい
古物商を行うには、申請時に実態のある「営業所」を登録する必要があります。この「営業所」とは、古物の売買やレンタルを行う拠点となる場所です。
営業所としてつかう場所が賃貸の場合、賃貸借契約書の使用用途が「事業用」である必要があります
個人事業主は自宅を営業所として計画している場合が多いでしょう。
自宅が賃貸物件であるときは、通常、この使用用途は「居住用」であることがほとんどです。
その時は別に営業所を借りる必要が出てきます。家賃等の費用も別途かかることとなり、営業所を準備できずに古物商許可の取得をあきらめる人も少なくはありません。
事業用の賃貸物件であっても、大家さんの使用承諾書が別途必要になる場合もあります。また、自己物件であっても分譲マンションであれば、マンション管理組合の承諾書が必要になることもあります。
個人事業主が古物商許可を取得する際には、この営業所の問題が大きく関わってきます。
副業でも古物商の営業ができる
最近ではインターネットの普及やコロナの影響により、在宅でできる副業の人気が高まっています。社会人の約23%ほどの人が副業を行っているともいわれています。
「安く商品を仕入れ手数料を上乗せして販売しその利益を得る」というせどりは、副業においても簡単で手の付けやすい人気の業種です。
「メルカリ」や「ラクマ」といったフリマアプリや、「ヤフオク」といったネットオークションでせどりを行うことができます。
ただしせどりにおいて、古物を扱う際には注意が必要です。特に、最近はメルカリの販売でも古物商許可は必要ですか?といった質問が多くあります。
販売目的で古物を仕入れ取引を行いますので、基本的に古物商許可を取得しなければなりません。
副業だから許可は不要、というわけではありませんので注意が必要です。また、副業で古物商を行う際には本業に影響の出ないようにしましょう。
古物商許可取得後に6か月以内に営業開始しなければならない
古物商許可を取得してから6ヶ月以内に営業を始めなければ、許可を取り消される可能性があります。
これは許可を取得して半年もの間、古物の営業をしない業者は今後も古物営業をしないとみなされてしまうからなのです。古物商許可取得と並行して開業する方は、スケジュールをしっかりと立てるようにしましょう。